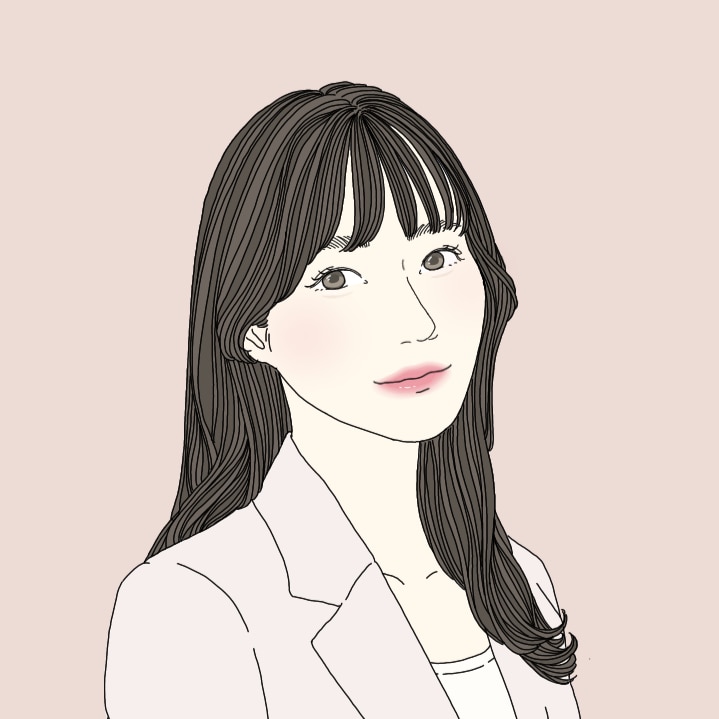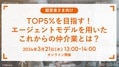二地域居住促進の全体像を解説。改正広域的地域活性化基盤整備法が2024年11月施行

近年、「二地域居住」や「二拠点居住」という言葉を耳にする機会が増えているのではないでしょうか。
この記事では、国土交通省が促進を進めている二地域居住について、メリットや法改正の概要を解説します。どのようなライフスタイルが想定されており、どのような取り組みを国が後押ししているのか確認してみましょう。
目次[非表示]
二地域居住とは
そもそも二地域居住とはどのような暮らし方を指すのでしょうか。国土交通省のホームページでは、二地域居住とは「都市部と地方部に2つの拠点を持ち、定期的に地方部でのんびり過ごしたり、仕事をしたりする新しいライフスタイルのひとつ」と定義されています。
具体的には、平日は利便性の高い都市部で働き、週末は地方部でゆとりのある田舎暮らしをする暮らし方が想定されています。

国土交通省のホームページでは、二地域居住は「地方部と都市部に2つの拠点を持ち、定期的に地方部でのんびり過ごしたり、仕事をしたりする新しいライフスタイルのひとつです。」と紹介されています
(出典:国土交通省「二地域居住」)
二地域居住のメリット
都市部と地方部を移動するための時間やコストがかかる二地域居住ですが、どのようなメリットがあるのでしょうか。二地域居住を実践する側(当事者・企業)と受け入れ側(地方部の住民・地方自治体)に分けて考えてみましょう。
まず、二地域居住を実施する当事者にとっては、都市部のみとは異なるゆとりある生活や、都市部を離れて得られる心身の健康や癒やしといったメリットがあるとされています。二地域居住を促進する企業としては、働き方改革や社会活動への貢献、社員の福利厚生の充実、新規ビジネス展開の契機といったメリットがあります。
一方、二地域居住を受け入れる地方部の住民には、地方部で深刻化する人手不足の解消やコミュニティの活性化につながるというメリットがあります。地方自治体も、遊休農地の解消や、雇用の創出、消費の増加などの経済効果を得られるでしょう。

二地域居住の「実践する側」「受け入れ側」双方のメリット
(出典:国土交通省「二地域居住」)
改正広域的地域活性化基盤整備法とは
二地域居住の促進を図る「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が、2024年5月2日に公布され、11月1日に施行されました。いったいどのような背景や狙いで整備された法律なのでしょうか。
人口減少は日本全体の課題ですが、特に地方部では人口減少が著しい地域もあり、住民の生活の維持が困難になる可能性も高まっています。このような状況において地域活性化を行うには、地方部への人の流れを生み出す必要性が高いため、二地域居住の促進によって地域課題を解決しようとしているのです。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機にリモートワークが一般化し、自然の多い環境を求める若者や子育て世帯の「二地域居住ニーズ」も高まっています。
二地域居住の普及・定着によって地方部の関係人口が増えれば、人口減少を食い止める手立てのひとつになると期待されています。
(出典:国土交通省「「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定」)
二地域居住促進に向けた改正法の概要
2024年11月1日に施行された二地域居住促進に向けた改正法は、どのような内容なのでしょうか。改正法においては、自治体による連携、官民の連携、関係者の連携という3つの観点から概要が示されています。二地域居住促進に向けた補助金とともに解説します。
二地域居住促進のための市町村計画制度の創設
都道府県と市町村の連携に向け、市町村による「特定居住促進計画」の作成が可能になりました。「特定居住促進計画」とは二地域居住促進の計画のことで、住民の意見を取り入れながら、二地域居住受け入れの方針や求める二地域居住者像をまとめ、公表します。地域と二地域居住希望者の適切なマッチングにつなげることが目的です。
加えて、市町村から都道府県に対し、都道府県が作成する「広域的地域活性化起案整備計画」の内容について提案を行うことが可能となりました。これは、二地域居住をサポートする拠点施設や重点地区を含む計画について、都道府県と市町村の連携をより一層強化することが狙いです。
二地域居住等支援法人の指定制度の創設
官民連携を促す内容として定められた法人指定制度は、不動産業界にとって非常に重要な施策ではないでしょうか。これは、二地域居住促進に取り組むNPO法人や不動産会社などの民間企業を、市町村長が「二地域居住等支援法人」として指定する制度です。
具体的には、二地域居住者に「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を提供する法人が支援法人として指定されます。たとえば、二地域居住に関する情報提供、二地域居住者への住宅提供やコワーキングスペースといった施設の整備、二地域居住の調査研究・普及啓発といった取り組みが挙げられます。
指定法人は、市町村長に対して、特定居住促進計画の作成・変更を提案することもできます。
二地域居住促進のための協議会制度の創設
関係者の連携のため、市町村が協議会を組織することも可能となりました。特定居住促進計画の作成にあたって、関係者との協議を行うことが目的です。
市町村や都道府県のほか、二地域居住等支援法人や地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所、農協などが構成員として想定されています。
(出典:国土交通省「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の施行について」)

「住まい」「なりわい」「コミュニティ」を二地域居住者に提供する法人が支援法人として指定されます
二地域居住促進に向けた補助金等の事業
法整備と連動して、どのような補助金事業が設けられているのでしょうか。
例を挙げると、空き家対策モデル事業においては、空き家を地域交流施設に活用するためのソフト・ハード両面の施策に対する補助金が設けられています。また、使われなくなった公共施設をコワーキングスペースに整備する事業においても、法人への補助があります。詳しくは、国土交通省がまとめている一覧をご覧ください。
(出典:国土交通省「二地域居住等関連施策一覧」)
目が離せない二地域居住
地方部での著しい人口減少や、I・U・Jターンを含む二地域居住のニーズを背景に、二地域居住のトレンドは今後強まっていくのではないでしょうか。住まいや働く場所、コミュニティなど、不動産事業との関連が強いため、今後も国土交通省や自治体の動きから目が離せません。
国土交通省は二地域居住のKPIとして、特定居住計画の作成数について5年間で累計600件、二地域居住等支援法人の指定数について5年間で累計600法人を掲げています。大きな動きが想定される二地域居住について、引き続き情報収集をしておきましょう。
LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。