賃貸不動産経営管理士の試験対策 「委任契約の性質」過去問を徹底解説
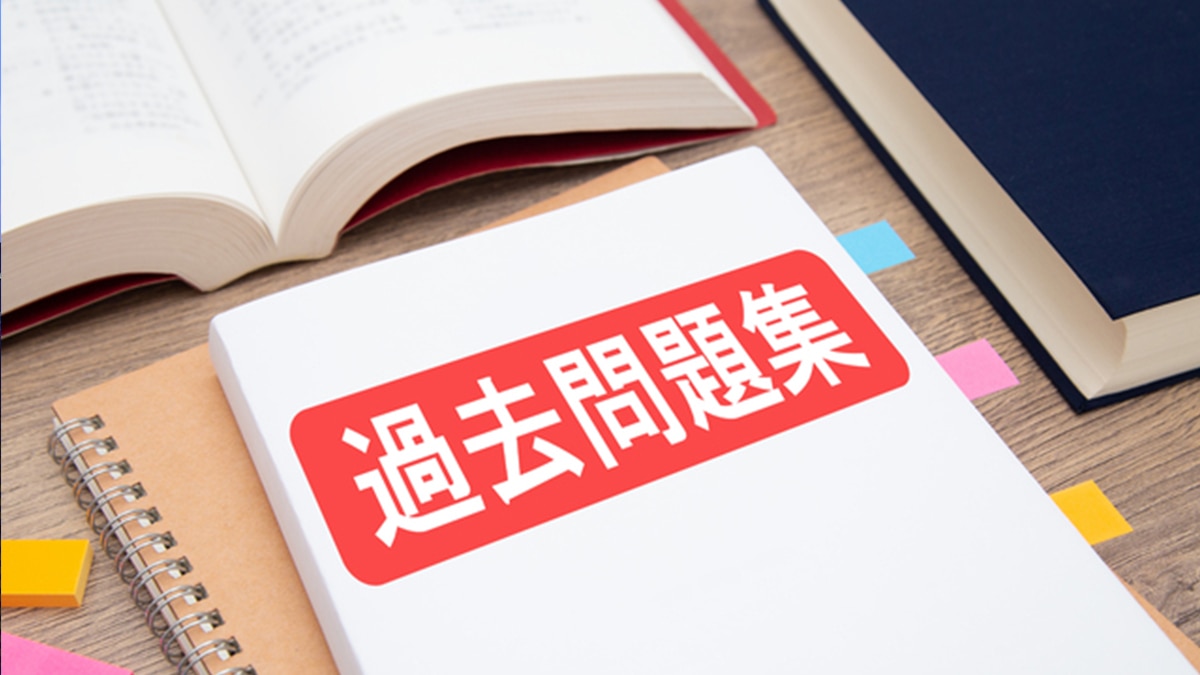
今回は、2024年度の賃貸不動産経営管理士試験の問5を使いながら、委任契約の性質について解説します。管理業者がオーナーから賃貸住宅の管理を受託する際に締結する契約は、民法上は委任と請負の性質を併せ持ちます。
委任契約については超頻出分野なので、対策をしている受験者が多かったのか、問5の正答率は87.8%でした。絶対に落とせない問題といえます。皆さまもぜひ問題にチャレンジしてみてください。
目次[非表示]
管理業者が受託する管理契約や特定賃貸借契約には委任の性質がある?
賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務(「賃貸住宅の維持保全を行う業務」又は「賃貸住宅の維持保全を行う業務」及び「家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務」を併せて実施する業務)を行う事業のこと賃貸住宅管理業といいます。
管理業者は、管理受託契約を締結して、これらの仕事を受ける場合もあれば、サブリース方式での賃貸管理を提案して、特定賃貸借契約を締結して、管理業務の一部を受ける場合もあります。(ただし、サブリース業者が入居者から受領する家賃等は、オーナーから委託を受けて受領するものではなく、サブリース業者が賃貸人として受領するものなので、賃貸管理業に含まれません)
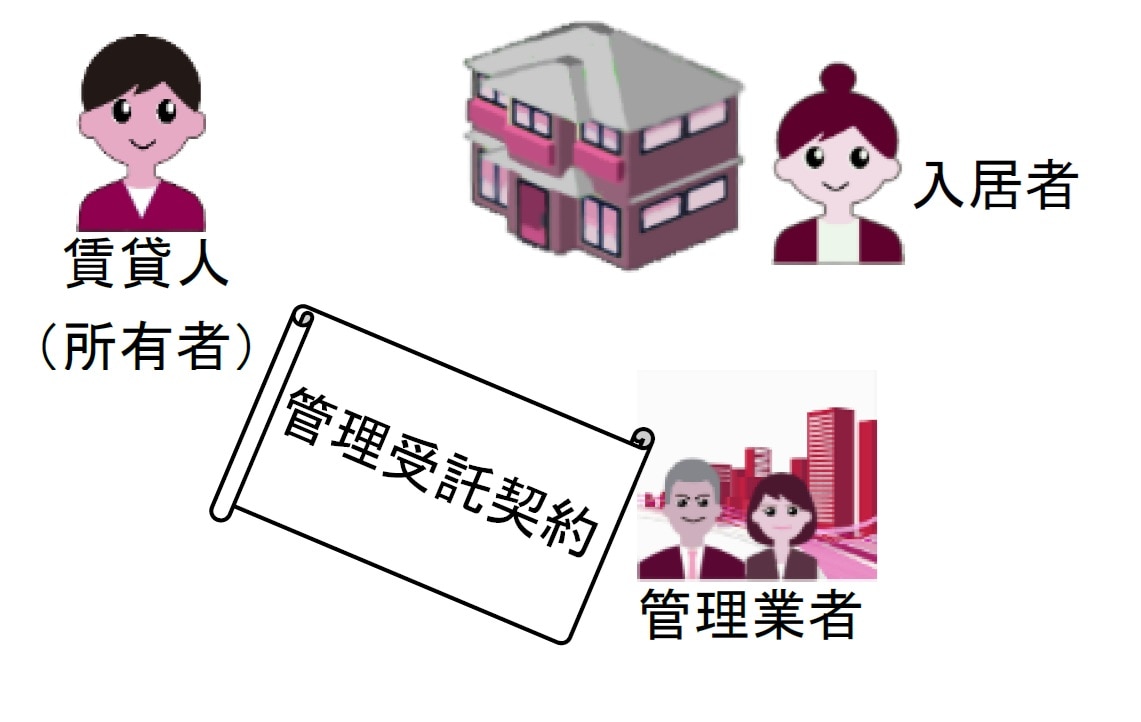
管理業者が受託する管理受託契約
委任契約の成立に書面の交付は不要?
委任契約は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立します(民法第643条)。これは口頭での申込みと承諾といった意思表示の合致のみで成立する「諾成契約」であり、契約書の作成は法律上の成立要件ではありません。
そもそも、契約は、法律に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に特定の方式は要求されていません(民法522条2項)。これを契約自由の原則と呼びます。委任契約もこの原則に従い、当事者の合意があれば口頭でも成立します。
とは言っても、賃貸管理業の実務では、管理業務の範囲(賃料の集金、滞納督促、クレーム対応、修繕の手配など)、管理委託手数料、契約期間、解約条件などを巡る後の紛争を避けるため、必ず「管理委託契約書」という書面を作成・締結するのが通常です。口頭での委託は、責任の所在や業務範囲が不明確になり、極めて高いリスクを伴います。
なお、賃貸住宅管理業者が管理受託契約を締結する場合や、特定転貸事業者(サブリース事業者)が特定賃貸借契約で賃貸住宅の維持管理業務を受ける場合には、契約書面を交付しなければ、監督処分の対象となります。
委任契約を解除するとどうなるの?
委任契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます(民法652条において準用する民法620条)。つまり、解除の時点から契約関係が消滅するのであり、契約当初に遡って契約がなかったことになるわけではありません。
委任契約は、賃貸借契約などと同様に、一定期間継続する継続的契約です。契約期間中に行われた事務処理やそれに対する報酬の支払いなど、既に行われた履行関係をすべて契約前に巻き戻す(遡及させる)ことは、法律関係を著しく複雑にし、非現実的です。そのため、解除の効果は将来に向かってのみ生じるとされています。
実際には、オーナーが管理会社との管理委託契約を月の途中で解約した場合、解約日までの管理業務(例えば、その月分の賃料集金やトラブル対応)については有効であり、管理会社はそれに対する管理委託手数料を日割りなどで請求できます。
委任はいつでも解約できるが急な解約の後は?
委任は、当事者の信頼関係を根本に置いているので、各当事者がいつでもその解除をすることができます(民法651条1項)。もちろん、相手方に不利な時期に解除した場合は、損害賠償責任を負う場合があります(同条2項)。
そして、委任契約が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者は、委任者やその相続人が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をする義務を負います。この義務は、受任者が死亡した場合には、その相続人や法定代理人も負います(民法654条)。
委任契約の終了によって、委任者の利益が害される事態(例えば、管理者がいなくなった不動産が放置され損害が拡大するなど)を防ぐため、受任者には契約終了後も一定の善後処理義務が課されています。これは委任契約の基礎となる当事者間の信頼関係から派生する、信義則上の義務と考えられます。
実際には、管理会社との契約が終了した直後に、管理物件で火災報知器が作動したり、大規模な漏水事故が発生したりした場合、オーナーやその後任の管理会社と連絡が取れないなど「急迫の事情」があれば、元の管理会社は、消防への通報や水道の元栓を閉めるなど、損害拡大を防ぐための最低限必要な緊急措置を講ずる義務を負うことになります。

委任の仕事が途中で終わっても報酬はもらえる?
委任契約が履行の途中で終了した場合、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができます。これは、その終了が委任者の責めに帰することができない事由による場合でも同様です(民法648条3項)。
受任者が既に行った事務処理の対価(労力)を保護し、当事者間の公平を図る趣旨です。契約が途中で終了したからといって、それまでの受任者の労力をすべて無に帰するのは不合理であるため、履行の割合に応じた報酬請求権が認められています。
たとえば、月の途中でオーナーとの管理委託契約が終了した場合を考えてみましょう。管理委託手数料が月額固定の場合、管理会社はその月の管理業務を月の途中まで行っているため、例えば日割り計算などによって、既に行った履行の割合に応じた報酬(管理委託手数料)をオーナーに請求することができます。
過去問にチャレンジ
【問題】
委任契約の成立及び終了に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2024年度問5)
1 委任契約は、書面による合意がなくても成立する諾成契約である。
2 委任契約が解除されて終了した場合、契約当初に遡って解除の効力が生じる。
3 委任契約が終了した場合、急迫の事情があるときは、受任者、その相続人又は法定代理人は、委任者、その相続人又は法定代理人が委任事務を処理することができるようになるまで、必要な処分をしなければならない。
4 委任契約が途中で終了した場合、その終了が委任者の責めに帰することができない事由によるときは、受任者は既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
正解:2
1〇 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる諾成契約である(民法643条)。
2× 委任契約の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(民法652条・620条)。
3〇 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(民法654条)。
4〇 受任者は、①委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときや、②委任が履行の中途で終了したときには、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法648条2項)。
●KENビジネススクール 田中嵩二氏の執筆記事
≫ 不動産業界で働いている人におすすめの資格4選
≫ 賃貸不動産経営管理士の勉強時間、学習の順番は? 短期間で合格するには
≫ 賃貸不動産経営管理士の過去問にチャレンジ! 重要事項説明書面の記載事項は
≫ 賃貸不動産経営管理士の過去問を徹底解説! 管理受託契約と重要事項説明











