不動産契約におけるクーリングオフとは? 宅建業法の判断基準と事例を紹介
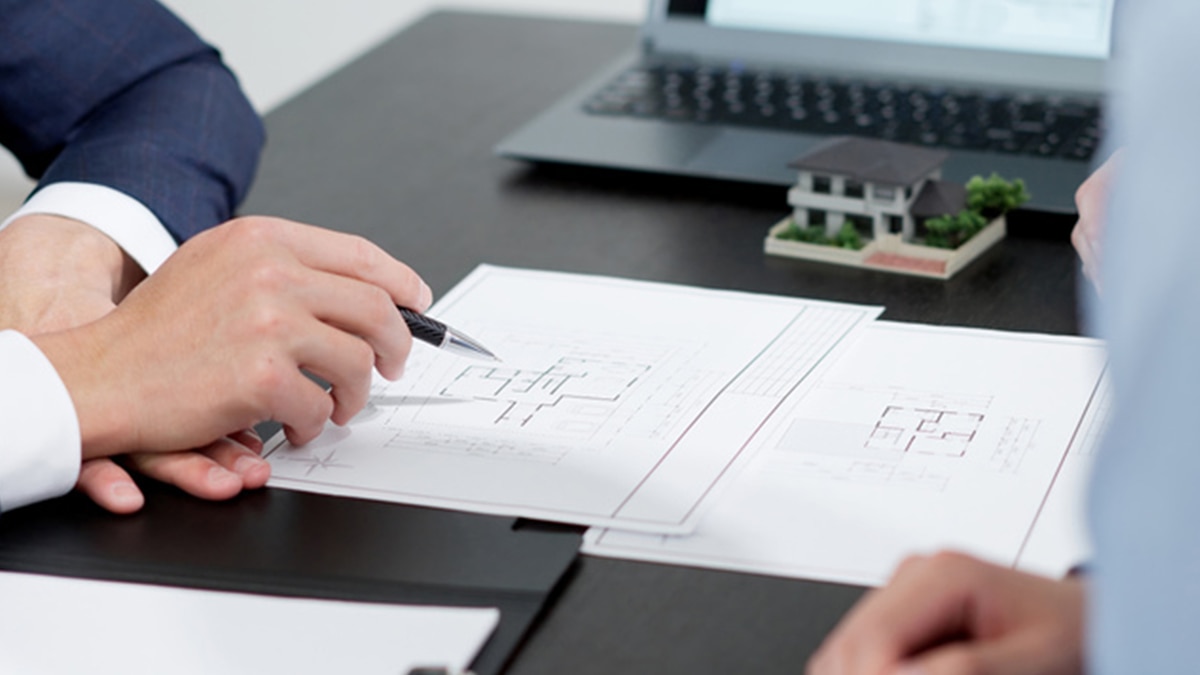
不動産契約では、買主からクーリングオフの申し出を受けることがあります。宅建業法で定められた条件を正しく理解していないと、適用の可否を誤ってトラブルに発展しかねません。
特に、契約場所・書面交付の有無・引き渡しの状況は、判断を左右する重要な要素です。制度の趣旨を踏まえ、適用できる場合とできない場合を整理しておくことが大切です。
この記事では、不動産契約におけるクーリングオフの概要・適用可否の具体例・対応時の注意点を解説します。クーリングオフ制度を正確に理解したい方はぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
不動産契約におけるクーリングオフとは? 宅建業法に基づく基本知識
クーリングオフとは、申し込みや契約後であっても一定の条件を満たせば、買主が一方的に契約を解除できる制度です。宅建業法は、専門知識のない買主が不利な契約を結ばされることを防ぐために、この仕組みを設けています。
不動産契約におけるクーリングオフの条件としては、以下のとおりです。
・売主が不動産会社(宅建業者)であること
・物件の引き渡しと代金の全額支払いが完了していないこと
・契約場所が「事務所」以外であること
・書面での説明から8日以内であること
クーリングオフ制度は消費者保護の観点から重要なため、適用条件や除外ケースを正しく理解することが大切です。以下で詳しく解説します。
宅建業法における不動産契約でクーリングオフが適用される4つの条件
ここでは、宅建業法に定められた、不動産契約でクーリングオフが適用されるための4つの条件を解説します。1つでも欠けると適用されないため、すべての条件を満たしているかを確認することが重要です。
売主が宅建業者で、買主が一般消費者であること
クーリングオフは、不動産の専門知識が乏しい買主を保護するための制度です。そのため、売主が宅建業者であり、買主が宅建業者以外の一般消費者である場合に適用されます。買主が個人か法人かは問いません。
下表は、売主・買主の属性ごとのクーリングオフの適用可否を整理したものです。
売主 | 買主 | 制度の適用 |
|---|---|---|
一般消費者 | 一般消費者 | できない |
一般消費者 | 宅建業者 | できない |
宅建業者 | 一般消費者 | できる |
宅建業者 | 宅建業者 | できない |
この表からわかるように、一般消費者同士や宅建業者同士の取引にはクーリングオフは適用されません。特に法人が買主となる場合は、「宅建業者に該当するかどうか」を登記簿や免許証明書で必ず確認しておくことが重要です。
代金の支払いがなく、引き渡しも完了していないこと
クーリングオフが適用されるには、代金の全額支払いと物件の引き渡しの両方が完了していないことも条件です。両方が済んでいる場合は契約が実質的に完了したと見なされ、制度の対象外となります。
たとえば、決済日に全額の振り込みが完了し、その日のうちに引き渡しも終わっていれば、買主はクーリングオフを行使できません。一方で、代金の一部のみを支払っており、引き渡しがまだの場合は制度を利用できます。
実務では支払いと引き渡しのタイミングがずれることも多いため、両者の状況を正確に把握しておくことが重要です。
契約が宅建業法上の事務所以外で締結されていること
クーリングオフは、冷静に判断できない状況で契約を結んだ買主を保護する制度です。そのため、宅建業法で定める「事務所または登録案内所」以外の場所で契約を結んだ場合に適用されます。具体的には自宅・勤務先・カフェなどで契約を結んだ場合が該当しますが、買主がこれらの場所を自ら指定していれば、制度の対象外となります。
また、近年増えているオンラインでの重要事項説明(いわゆるIT重説)や電子契約については、買主が自宅で対応した場合、リラックスした状態で聞いていると判断されると、同様に適用外となる可能性があります。
契約場所と指定の有無は、制度の適用判断に直結するため、必ず記録として残すことが重要です。特にオンライン取引においては、宅建業法の解釈が曖昧になりやすく、慎重な対応が求められます。
書面での説明から8日以内であること
クーリングオフを行使できる期間は、宅建業者が制度の説明書面を交付した日を起算日として8日間です。この期間を過ぎると原則として行使できません。
一方で、書面での説明が行われていなかった場合は、8日を過ぎても適用される可能性があります。ただし、代金の全額支払いや引き渡しが完了している場合は対象外となる点も重要です。
実務では、書面交付の有無や交付日を明確に記録しておくことで、後々のトラブル防止につながります。

不動産契約でクーリングオフが適用されるには、締結場所や期間などの条件があります
クーリングオフの適用可否がわかる不動産契約の具体事例
クーリングオフの適用可否は、契約の場所や買主の行動によって大きく変わります。ここでは、実務でよく見られる2つの事例を挙げて、適用できる場合とできない場合を詳しく解説します。
事例1.買主が勤務先で契約し、場所の指定をしていなかった場合【クーリングオフできる】
勤務先での契約は、買主が場所を指定していない限りクーリングオフの対象となります。宅建業法におけるクーリングオフには、冷静に判断できない状況で契約した買主を保護する趣旨があるためです。
たとえば、営業担当者が突然勤務先を訪問し、その場で売買契約を締結したケースは「事務所以外での契約」に該当します。買主が自ら場所を指定していないため、制度が適用されるのです。
実務では、契約場所が買主の意思によるものかどうかを明確に記録しておくことが重要です。
事例2.買主がモデルルームを訪れ、その場で契約した場合【クーリングオフできない】
買主が自らモデルルームや案内所を訪問し、その場で契約した場合はクーリングオフの対象外となります。宅建業法上、モデルルームや案内所は「事務所等」に該当し、買主の意思で訪問したと判断されるためです。
一方、期間限定で設置された臨時案内所や、宅建士が常駐していない案内スペースなどは「事務所等」に該当しない可能性があります。この場合、契約場所や条件によってはクーリングオフが適用されることもあります。
実務では、契約場所が宅建業法上の「事務所等」に該当するかどうかを確認し、正しく区分しておくことが重要です。

クーリングオフの適用可否について事例で確認してみましょう
不動産契約の際の3つの注意点
クーリングオフを避けるためには、宅建業法に沿った手続きと買主への適切な対応が不可欠です。ここでは現場で実践できる3つの注意点を解説します。
契約は必ず宅建業法上の事務所で締結する
契約は、必ず宅建業法で定める「事務所」で行うことが重要です。これは、買主が落ち着いて判断できる環境を確保するための基本です。
宅建業法上の事務所とは、宅地建物取引士を配置すべき場所が該当し、具体例としては以下のような場所が挙げられます。
・不動産会社の店舗や本社事務所
・登録済みの案内所(モデルルームや販売センターなど、行政庁に届け出されているもの)
・宅建業法上の事務所として登録されているモデルルーム
なお、未登録の販売スペースや臨時のイベント会場は「事務所等」に該当せず、このような場所で契約した場合はクーリングオフが適用される可能性があります。
契約場所が要件を満たしているか、事前に必ず確認しましょう。
営業トークは誤解を招かないよう、根拠を明示して説明する
営業時の発言が買主の不安や誤解を招くと、契約後にクーリングオフを行使される原因となることがあります。たとえば、「ほかにも検討している人がいる」「本日中の申し込みで値引き可能」といった発言は心理的圧力と受け取られやすいため注意が必要です。
特に、販売状況や条件提示の理由を十分に説明せずに急がせると、不信感を抱いた買主が後から制度を利用するケースも見られます。発言には必ず根拠を添え、条件や背景を正確に説明することが重要です。
説明義務の履行と書面の交付記録を徹底する
売主が宅建業者で買主が一般消費者の場合や、事務所以外での不動産契約を行う場合など特定の条件下では、クーリングオフ制度の説明と書面の交付が義務付けられています。説明が不十分だったり、交付の記録が残っていなかったりすると、買主が契約後に解除できる状態をつくってしまう恐れがあります。
たとえば、口頭で説明しただけで交付日や受領印が確認できない場合、8日を過ぎてもクーリングオフが認められるケースがあります。交付書類には必ず日付と署名を残し、電子交付を行った場合は送信ログや開封記録も保管することが重要です。
証跡を確実に管理することが、将来的なトラブル防止につながります。

後々のトラブルとなることを避けるため、宅建業法に沿った手続きと、買主への適切な対応が求められます
まとめ
不動産契約のクーリングオフは、売主が宅地建物取引業者であり買主が一般消費者であること、代金の全額支払いや引き渡しが完了していないこと、契約が事務所や登録案内所以外で締結されていること、さらに書面交付後8日以内であることの4要件がそろった場合に成立します。
クーリングオフ制度は、買主が冷静に判断できる環境を確保するためのものであり、事務所や登録案内所での契約、買主が場所を指定した場合、または一般消費者同士・業者間の取引には適用されません。
実務では、契約を事務所など適切な場所で行うこと、説明に根拠を示すこと、書面や電子交付の履歴を正しく残すことなどの対応を行うことでトラブル防止につながります。
クーリングオフ制度の内容を正確に理解し、適切に対応していきましょう。
■関連記事
≫ 【2025年版】不動産取引に関する法律一覧
≫ 重説に追加された重要土地等調査法とは? 不動産取引への影響を解説
≫ 嫌悪施設を一覧で確認 | 調べ方や不動産会社が果たすべき告知義務を解説
≫ 告知事項に該当する内容は? 説明義務の期間や告知を怠る影響
LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。
≫ LIFULL HOME'S Businessコラム
≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧











