特定賃貸借契約の重要事項説明書、どこまで記載すべき? 賃貸不動産経営管理士過去問解説

今回は、2024年度の賃貸不動産経営管理士試験の問37を参考にして、賃貸住宅管理業法におけるサブリース方式の重要事項説明について解説します。
本問は、特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約の重要事項説明書に記載すべき事項を問う問題です。この問題は、賃貸住宅管理業法および同法施行規則(以下、規則)に基づく重要事項説明の知識を試すもので、実務での正確な運用が求められる内容です。
本記事では、制度内容と趣旨、具体例、実務上の運用や問題点を詳しく解説します。
なお、サブリース方式における重要事項説明については毎年必ず出題されています。したがって、本問の正答率は60.9%と高めでした。
皆さまもぜひ問題にチャレンジしてみてください。
特定賃貸借契約重要事項説明書には何を記載すべき?
特定賃貸借契約とは、賃貸住宅の賃貸人(オーナー)と特定転貸事業者(サブリース事業者)との間で締結されるマスターリース契約を指します。これは、事業者が賃貸住宅を一括借上げ、第三者(入居者)に転貸する事業を目的としたものです(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第2条第4項)。
この契約の締結前に、特定転貸事業者は相手方(賃貸人)に対して重要事項説明を行い、説明書を交付・説明しなければなりません(同法第30条)。重要事項説明書の記載・説明すべき事項は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(以下、施行規則)第46条に定められています。
記載事項の概要は以下の通りです。
- 特定賃貸借契約を締結する特定転貸事業者の商号、名称又は氏名及び住所
- 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅
- 特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全の実施方法
- 特定転貸事業者が行う賃貸住宅の維持保全に要する費用の分担に関する事項
- 特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
- 責任及び免責に関する事項
- 契約期間に関する事項
- 転借人の資格その他の転貸の条件に関する事項
- 転借人に対する第四号に掲げる事項の周知に関する事項
- 特定賃貸借契約の更新及び解除に関する事項
- 特定賃貸借契約が終了した場合における特定転貸事業者の権利義務の承継に関する事項
- 借地借家法その他特定賃貸借契約に係る法令に関する事項の概要
なお、説明担当者の資格について、法律上は宅地建物取引士や賃貸不動産経営管理士である必要はなく、営業所等に配置される業務管理者(賃貸不動産経営管理士又は宅地建物取引士の資格を有する者がなることができます)の管理・監督の下で、事業者内で適切な知識を持つ者が対応します。ただし、実務では資格者が関与することが慣行として多いです。
なぜ重要事項説明の義務があるの?
この制度の目的は、賃貸人(オーナー)が契約内容を十分に理解し、トラブルを未然に防ぐことです。
賃貸住宅管理業法は、2017年の改正でサブリース問題(家賃減額や契約解除のトラブル)を背景に導入され、透明性と公平性を確保することが狙いです。
賃貸不動産経営管理士や宅建士が説明に立つことは、信頼性向上や行政指導回避のため推奨されますが、法的強制力はありません。2025年現在、大手事業者は資格者を配置する傾向が強まっています。
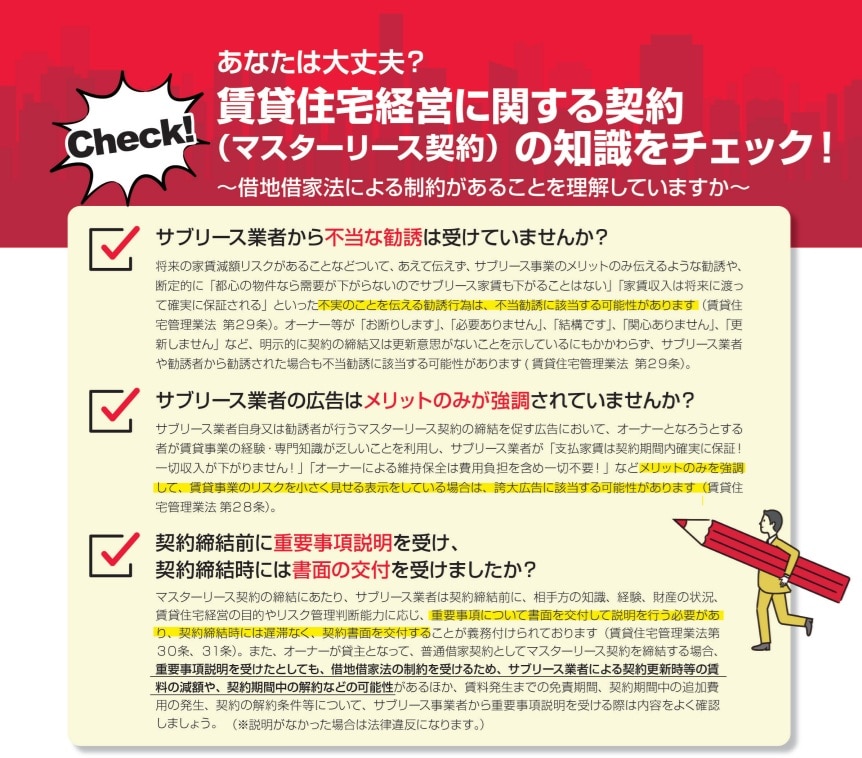 国土交通省 賃貸住宅経営(サブリース方式)の注意管理リーフレット。国土交通省は賃貸住宅管理業法ポータルサイトでサブリース契約に関する情報を提供しています
国土交通省 賃貸住宅経営(サブリース方式)の注意管理リーフレット。国土交通省は賃貸住宅管理業法ポータルサイトでサブリース契約に関する情報を提供しています
選択肢の設問ごとに解説
(1)特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の建物設備
前記施行規則第46条第2号では、重要事項説明書に「特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅」を記載・説明することを義務付けています。これは、賃貸住宅の名称、所在地、構造、階建、戸数、面積、建物設備、附属施設などを含みます。建物設備(例: 水道、ガス、エレベーターなど)は、対象物件の概要として必須です。
これは、サブリースでは物件の状態が家賃や維持保全に直結するため、曖昧さを排除し、トラブル防止を図ることが目的です。過去のサブリース問題(家賃減額紛争)で物件詳細の誤認が多かった背景から、透明性を確保する狙いです。
たとえば、マンションオーナーAさんがサブリース業者B社と契約する場合、説明書に「所在地: 東京都渋谷区、構造: RC造5階建、戸数: 20戸、建物設備: 都市ガス、上水道、公共下水、BSアンテナ、エレベーター」等と記載します。Aさんが設備の老朽化リスクを把握できるようにするわけです。
(2)賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合は、その旨
施行規則第46条第8号は「責任及び免責に関する事項」を記載・説明することを定めていますが、これは事業者が責任を負わない場合(天災等)や、賃貸人が賠償責任保険等に加入する場合、その保険対応損害について事業者が責任を負わない旨に限ります。
賃貸人が保険に加入しない場合の説明は義務付けられていません。法的には、保険加入は賃貸人の任意のため、未加入を積極的に記載する要件はありません。
これは、責任分担を明確にし、損害発生時の紛争を防ぐことが目的です。事業者の免責範囲を限定し、賃貸人の保険加入を促すことでオーナー保護を図りますが、未加入の説明を義務化しないのは、賃貸人の選択自由を尊重するためです。サブリーストラブルで保険未加入による損失が問題化したため、加入ケースの透明性を重視しています。
たとえば、オーナーAさんが保険未加入の場合、説明書に記載する必要はありませんが、加入する場合、「賃貸人は賠償責任保険に加入し、火災等の保険対応損害については事業者B社が責任を負わない」と記載します。
(3)特定転貸事業者が行う維持保全の実施状況を賃貸人へ報告する頻度
施行規則第46条第6号では、「特定賃貸借契約の相手方に対する維持保全の実施状況の報告に関する事項」を記載・説明します。これには報告の内容、方法、頻度(年1回、半年1回等)が含まれます。維持保全は点検、清掃、修繕等を指し(法第2条第2項)、報告は賃貸人保護のための必須事項です。
これは、賃貸人が物件の状態を定期的に把握し、管理の質を監視できるようにするためです。サブリースで事業者の怠慢が問題化したため、報告義務を課し、透明性を高めます。頻度指定は、賃貸人の不安を軽減し、早期対応を促す狙いです。
たとえば、サブリース業者B社が「維持保全実施状況を年2回(6月・12月)、報告書(写真・修繕履歴付き)で郵送またはメール」と記載すると、Aさん所有のマンションで、清掃頻度や修繕記録を報告し、Aさんが遠隔監視可能になるわけです。
(4)特定賃貸借契約の期間は家賃が固定される期間ではない旨
施行規則第46条第9号では、「契約期間に関する事項」を記載・説明します。これには始期、終期、期間のほか、家賃が固定されないこと(借地借家法第32条による変動可能)を明記。普通借家契約か定期借家かを指定します。
これは、賃貸人が家賃固定の誤認を防ぎ、市場変動リスクを認識させることが目的です。過去のサブリースで「長期固定保証」の誤解が紛争を招いたため、借地借家法の適用を明確にし、オーナー保護を強化しています
たとえば、契約期間10年でも、「期間中、家賃は借地借家法により変動可能で固定保証ではない」と記載することで、B社が市場下落で減額請求した場合、Aさんは協議可能だが、事前説明でトラブルを回避できるわけです。
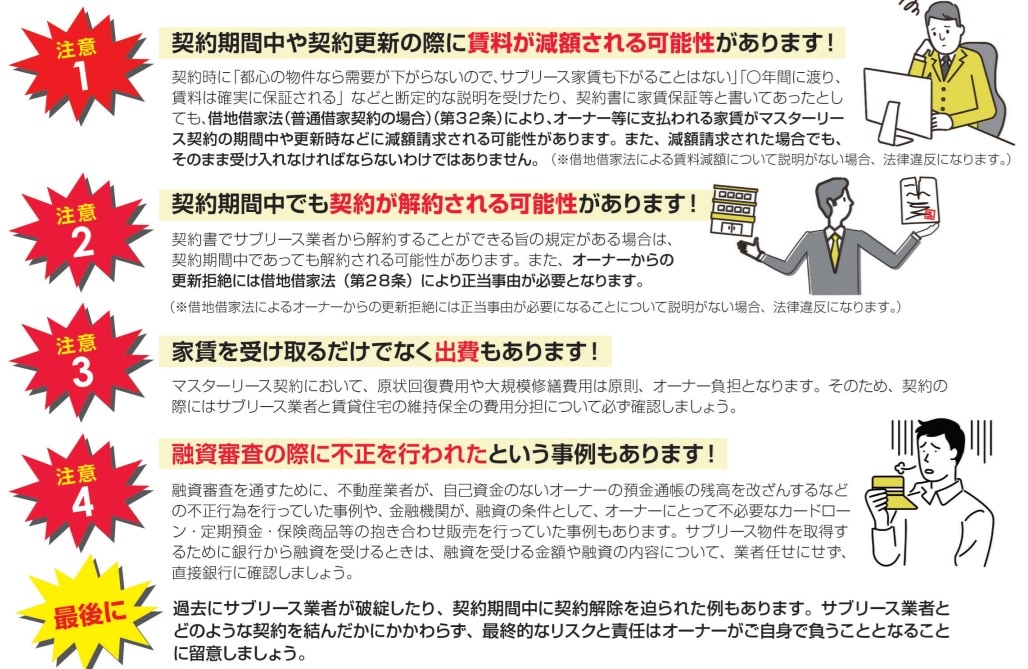 国土交通省 賃貸住宅経営(サブリース方式)の注意管理リーフレットより、契約時の注意点
国土交通省 賃貸住宅経営(サブリース方式)の注意管理リーフレットより、契約時の注意点
過去問にチャレンジ
【問37】
特定転貸事業者が行う特定賃貸借契約重要事項説明において、特定賃貸借契約の相手方になろうとする者に交付すべき書面(以下、各問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という) に記載して説明すべき事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(2024年度問37)
- 特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅の建物設備
- 賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合は、その旨
- 特定転貸事業者が行う維持保全の実施状況を賃貸人へ報告する頻度
- 特定賃貸借契約の期間は家賃が固定される期間ではない旨
正解:2
1は正しい。特定賃貸借契約重要事項説明書には、特定賃貸借契約の対象となる賃貸住宅が記載されるべきであるところ、建物設備もこれに含まれる(規則第46条第2号)。
2は誤りで、正解。特定転貸事業者が責任を負わないこととする場合や賃貸人が賠償責任保険等へ加入をすることについては説明事項となるが(規則第46条第8号)、賃貸人が賠償責任保険に加入しない場合は、その旨を説明する必要はない。
3は正しい。特定転貸事業者が行う維持保全の実施状況を賃貸人に報告する内容や頻度は、説明事項に含まれる(規則第46条第6号)。
4は正しい。契約期間は家賃が固定される期間ではないことについて説明が必要であるとされている(規則第46条第9号)。












